天正3年(1575年)4月、島津家久(しまづいえひさ)は入京。しばらく京に滞在してあちこち見てまわることになる。織田信長の軍勢が出征から戻ってきたところにも出くわす。『中務大輔家久公御上京日記』では、そのときのことも詳しく記される。
なお日記の日付は、旧暦となっている。
前回の記事はこちら。山崎に着いたところまで。
『中務大輔家久公御上京日記』についてはこちら。
史料は東京大学史料編纂所の翻刻より引用。
『中務大輔家久公御上京日記』(東京大学史料編纂所ホームページ)
島津家久については、こちらの記事にて。
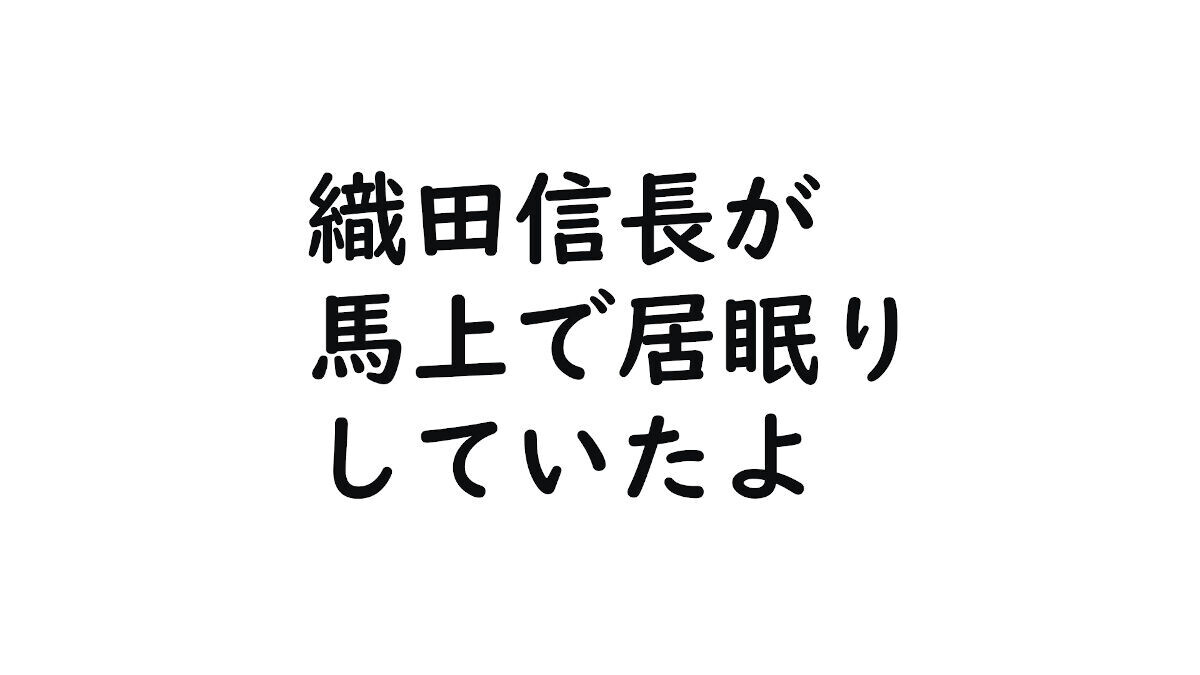
天正3年4月17日、嵐山から愛宕山へ
十七日、打立行は、ひたりの方ニ小倉の明神の鳥居有、儅、行て右方ニしうりう寺とて細川兵部大輔殿の城あり、猶行て左方松尾、次に法輪寺、其邊ニこかうの局の居給ひし所とて跡はかり有、其次に嵐山、其邊ニとなせの瀧、大井川を渡り、やかて天龍寺の前ニこかうの石塔とて桜の木本に有、亦天龍寺の邊ニ芹川、其うしろに亀山とて有、儅、行て嵯峨の町にしはしの間中宿仕候て、やかて打立、清瀧川にてはらひなと有て、愛宕山へ参、坊中一見、さて長床坊へ一宿、
山崎を発つ。いよいよ山城国に入った。道中では左手のほうに「小倉の明神の鳥居」が見えた。たぶん小倉神社(おぐらじんじゃ、京都府乙訓郡大山崎町円明寺)の鳥居であろう。そして右手のほうには勝竜寺城(しょうりゅうじじょう、京都府長岡京市勝竜寺)が見えた。この城は「細川兵部大輔殿」の城であると説明している。細川藤孝(ほそかわふじたか、細川幽斎)のことだ。
さらに行くと、左手のほうに松尾社(松尾大社、京都市西京区嵐山宮町)が見え、次に法輪寺(西京区嵐山虚空蔵山町)がある。そして、小督局(こごうのつぼね)の住んだところがあった。そして嵐山に入り、戸無瀬滝(となせのたき)を見て、大井川(大堰川)を渡ると、天龍寺(てんりゅうじ、京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町)の前の桜の木の下に小督局の石塔があった。渡月橋近くの小督塚のことだろうか。
小督局は『平家物語』にも登場する。藤原成範(ふじわらのしげのり)の娘で、信西(しんぜい、藤原通憲、みちのり)の孫にあたるという。箏の名手であり、美貌でも知られていた。中宮の平徳子の紹介で高倉天皇に仕えて寵愛を受けるが、平清盛(徳子の父)により宮中から追放された。その後は嵯峨に隠れ住んだとされる。
天龍寺のあたりに芹川(せりかわ)があり、そして亀山(右京区嵯峨亀山町)があり。嵯峨の町でちょっと休憩してから、山に入る。清瀧川をわたって、愛宕山(愛宕神社、京都市右京区嵯峨愛宕町)を参詣。愛宕山の坊を見学してまわる。この日は愛宕山の長床坊に泊まる。
天正3年4月18日、目的の一つを果たす
十八日、早朝愛宕山より嵯峨ニ罷下候、大百味之像、軽く成かたき由ありし間、南覚坊跡ニ召置、十九日ニ成就、
早朝に愛宕山から下山して嵯峨に戻る。
「大百味之像」については『旧記雑録』収録の『家久君上京日記』では「大百味之儀」とある。「像」ではなく「儀」のほうが正しいかな? と。「大百味之儀」という儀式を執り行ったというほうが意味が通るように思う。「大百味之儀」は簡単には終わらないものだったので、南覚坊をここに残して任せた。翌日の19日に成就した。
ちなみに日記の始まりのほうで、愛宕山参詣は旅の目的の一つとして出てきている。
天正3年4月19日、能を楽しむ
十九日、嵯峨一見、先二尊院、さて二尊院の邊に西行の菴室の跡有、其より東ニのゝミや有、さて帰り候へハ、愛宕より御使僧百味之御札、御供使僧酒寄合候、其より申剋に嵯峨の尺加堂の前にて祭礼有、儅、丹波の日吉大夫来り、舞臺なとかさり候へ共、大雨にて尺迦堂の内にて能有、
嵯峨の街を見物。二尊院(京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町)を見る。西行(さいぎょう)の庵跡もあった。そこから東へ、野々宮(野宮神社、右京区嵯峨天龍寺立石町)があり。見物から戻ると愛宕山の使いの僧が「百味之御札」も持ってきた。そして使僧をもてなす酒宴を開いた。
申の刻(午後4時頃)に嵯峨尺迦堂(嵯峨釈迦堂か、京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町)で祭礼があり、「丹波の日吉大夫」の能があった。舞台などが飾り付けられていたが(屋外だろう)、大雨だったの尺迦堂(釈迦堂)の中で行われた。
「丹波の日吉大夫」は猿楽の一座か。
天正3年4月20日、細川殿の館跡は荒れ果てて
廿日、打立行ハ、左方ニ廣澤の池有、亦右ニ千代のふる道とて有、さて行て御しょの御影たう有、やかて北野の天神へ参、儅、上京ニ打立、細川殿舘一見、今は荒終て跡はかり有、其より下京与介といへるものゝ親の所へ一宿、仏具也、
嵯峨を発ち、左手に広沢池(京都市右京区嵯峨広沢町)を見ながら東へ、右手のほうには「千代の古道」もあった。さらに行くと「御所の御影堂」。これは仁和寺(にんなじ、右京区御室大内)の御影堂のことらしい。そして北野天神(北野天満宮、京都市上京区馬喰町)を参詣した。
上京のほうへ向かう。「細川殿舘」を見学する。今は荒れ果てて館の跡が残る。こちらは細川勝元(ほそかわかつもと)の邸宅跡だろうか。現在の京都市上京区上小川町のあたり。細川勝元は幕府の管領で、応仁元年(1467年)から文明9年(1477年)にかけての「応仁の乱」では東軍を率いた。
下京で一宿。「仏具也」というのは、仏具を扱う商家だった、ってことか?
天正3年4月21日、織田信長を見る
廿一日、紹巴へ立入候、やかて心前の南をかされ宿と定候、さて織田上総殿、おさかの陣をひかせられ候を心前同心ニて見物、下京より上京のことく馬まハりの衆打烈、正国寺の宿へつかせられ候、さてのほり九本有、黄礼藥といへる銭の形をのほりの紋ニつけられ候、儅、上総殿の前にほろの衆廿人、母衣の色ハさたまらす候、是ハ弓箭ニおほへの有衆にゆるさるゝといへり、さて馬まハりの衆百騎計也、引陣ニて候へ共、各々鎧を被着候、亦馬面・馬鎧したるも有、亦虎の皮なとを馬にきせたるも有、亦馬衣・尾袋なとをしたる馬三疋、上総殿乗替とてさゝせられ候、上総殿支度皮衣也、眠候てとをられ候、十七ヶ國の人数にて有し問、何万騎ともはかりかたきよし申候、
京では里村紹巴(さとむらじょうは)の世話になる。心前(しんぜん)の屋敷の南側を宿に定めた。里村紹巴は超大物の連歌師で、心前はその弟子である。里村紹巴は島津氏と交流があり、とくに樺山善久(かばやまよしひさ)と昵懇だった。樺山善久は島津家久の舅(妻の父)である。樺山善久が「うちの婿が京に行くから、面倒みてやってね」と前もってお願いをしていたのだろう。
この日、織田上総殿(織田信長)が大坂の陣(石山本願寺攻め)から凱旋してきたというので、心前と連れ立って見物に行く。下京から上京へ、馬廻り衆を引き連れて「正国寺」へと向かうところだった。「正国寺」は相国寺(しょうこくじ、京都市上京区烏丸通寺之内上る東入相国寺門前町)のことで、織田信長はここを今日での定宿としていた。
島津家久は織田軍の様子を詳細に記している。
幟が9本。「黄礼藥といへる銭の形をのほりの紋ニつけられ候」というのは、黄地に永楽通宝の入った幟旗のことだろう。織田信長の前に母衣衆(側近の精鋭)が20人いて、母衣(背につけた布)の色はさまざま。母衣衆はとくに腕が立つ者たちばかりであるという。馬廻衆は100騎ばかりで、引き陣だけど甲冑姿。馬も面や鎧をつけていて、虎皮を着せたものもある。また、馬衣(うまぎぬ)や尾袋を着せた馬も3匹いて。こちらは上総殿(織田信長)が乗り換える馬なんだとか。上総殿(織田信長)は皮衣(かわぎぬ、毛皮の上着)を着ていた。馬上で居眠りをしながら通り過ぎていった。兵は17ヶ国から集まっていて、何万騎いるのか数え切れない。
じつによく観察している。数字も細かい。
居眠りをしていた織田信長に対して、島津家久はいかなる印象を持ったのだろうか?
つづく……
<参考資料>
『中務大輔家久公上京日記』
翻刻/村井祐樹 発行/東京大学史料編纂所 2006年
※『東京大学史料編纂所研究紀要第16号』に収録
鹿児島県史料『旧記雑録 後編一』
編/鹿児島県維新史料編さん所 発行/鹿児島県 1981年
『島津国史』
編/山本正誼 出版/鹿児島県地方史学会 1972年
鹿児島県史料集13『本藩人物誌』
編/鹿児島県史料刊行委員会 出版/鹿児島県立図書館 1972年
鹿児島県史料『旧記雑録拾遺 諸氏系譜三』
編/鹿児島県歴史資料センター黎明館 発行/鹿児島県 1992年
ほか

